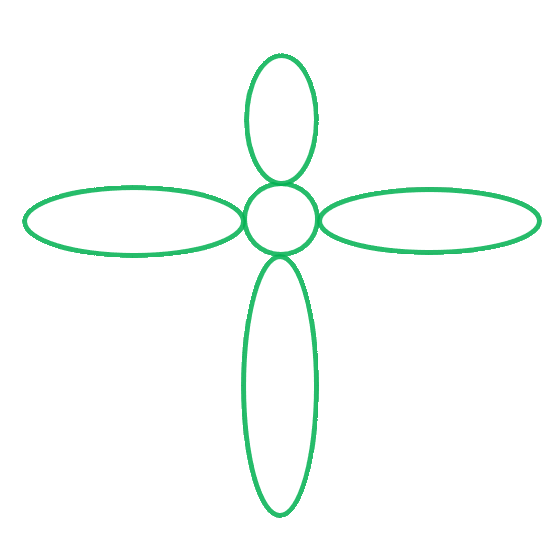ステパノ宮岸進(司祭) 代表牧師 逝去のお知らせ
当ユニバーサル福音教会の代表牧師、ステパノ宮岸進司祭が去る11月18日 午前9時20分にご逝去されました。享年89歳。
ステパノ宮岸進牧師は、当ユニバーサル福音教会(エキュメニカル派の単立教会)の設立者の一人であり、代表牧師をされてきました。キリスト教界諸派の一致(エキュメニカル)運動だけでなく、超宗教の集いでも諸宗教和合の先頭に立たれようと尽力されました。日本のブライダル宣教では、当時、全日本ブライダル協議会をカトリックの(故)チプリアーノ神父や日本基督教正教師、(故)三田和芳先生と共に、日本特有の非キリスト者の結婚式を福音と祈りで臨むブライダル宣教の先頭に立たれました。数年前より、肝臓がんや脳梗塞等で体調を崩され、療養生活を送っておられました。病状は一進一退。幾度か入退院を繰り返し、老衰によりついに霊界に旅立っていかれました。
ユニバーサル福音協会
共同代表牧師 ミカエル御国新一
司祭自叙伝
信・望・愛
ー私の85年の軌跡ー
元日本聖公会司祭
ステパノ 宮岸 進
ユニバーサル福音協会 代表
目次:
第一章 生い立ち
・ 【両親の出自】
・【終戦を境に混乱した教育】
・【「自殺」を考えるほどの試練】
・【友達に誘われて教会へ】
・【父を越え、難関の泉丘高校入学】
・【大和百貨店での勤務】
第二章 聖職者として
・【神学校へ、そして夏季勤務】
・【伝道者として生きる決意】
・【新天地・加悦へ、そして結婚】
・【妻と歩んだ二人三脚】
・【金沢聖ヨハネ教会でのあゆみ】
・【福祉事業拡大への落とし穴】
・【借金の返済での苦労と反省】
第三章 新たな出会い、ブライダル宣教とエキュメニカル運動
・【新たな出会い(再会)】
・【ユニバーサル福音教会の設立】
・【イエス・キリストの戴冠式でイスラエルへ】
・【変革期を迎えている聖公会】
第四章 座右の銘「信仰・希望・愛」
*編集にあたって
この“私の85年の軌跡”(回顧録)は、長年記者活動をしてこられた日下一彦氏に依頼して5回のインタビュー(録音記録有)を行った後に書き起こしたものを御國氏が編集しました。宮岸司祭(先生)の癌が全身に転移し担当医から余命約6ヶ月の宣告を受けた令和2年6月から7月にかけて先生の意向も踏まえて1回に1時間程のインタビューを御國氏も交えて日下氏が記録しました。京都弁に近い金沢弁が各所に見られるのも先生をご存知の方は親しみをもって読めるようにとも思いそのままで書かれてあります。登場する人物名は出来る限りイニシャルにさせて頂きました。 ( Copy-right@ユニバーサル福音教会)
はじめに
宮岸 進 司祭は、中学三年生の時、聖公会の信徒だった友人に誘われてキリスト教会の門をくぐり、その後、高校生の時(16歳)洗礼を受け、今日までイエス・キリストが示された人々に対する愛を実践し続けてきた。それは社会の片隅で、人知れず苦労する人々に寄り添って尽す生涯だった。この回顧録は、師の85年に及ぶ生涯と、聖職者として歩んだ信仰の軌跡を振り返ったものである。

第一章 生い立ち
ボクは1935年(昭和10年)7月15日、金沢市十三軒町で生まれました。市内を流れる犀川のそばです。先祖代々浄土真宗の家系でした。ボクは現在85歳です。ボクが8歳、妹の美恵子が4歳の時、父・辰夫が感染症で亡くなり、その時はとても寂しかった。父は中耳炎で入院し、退院してそのお祝いをした矢先、食べた物が悪く、それにあたったようです。享年38歳の若さで、その時母の美伸(みしん)は35歳でした。父の逝去後、母は再婚しないでボクらを育て、70歳で天に召されました。

【両親の出自】
父は石川県津幡町の出身で、実家は庄屋で地主でした。屋号を「天商」といい、米作の他、山を持ち、桐を切り出していた。はなれもあるほどの大きな家で、便所も奥に二つありました。土蔵も二つ建っていて、一つはお米を納める蔵でした。財力の豊かな家のようでした。家系をみると、平安末期の武将、木曽義仲の義理の兄弟で、今井兼平に遡ります。その末裔が今も津幡町に住んでいます。
オヤジは旧制金沢二中(現在の紫錦台中学校)に在学中、卒業を待たずに京都の大和に就職しました。商売に長けとったんやないかね。後に金沢に宮市大和が出来ると、そんな時に金沢に異動し、亡くなった時は呉服部門の部長をしとった。
母は富山県福野町の出身で、実家は母の方も地主で、福野平野の真ん中にある「八塚」と呼ばれる集落でした。母は「みしん」という名がイヤやもんで、「みのぶ」と言うとった。母の実家も庄屋でした。兄姉だけで9人おるんですけど、そのうち7人が女です。それを全部嫁がせたんですから、かなり財力があったんでしょうね。
当時、母は砺波女学校に通っていました。片田舎の農村から女学校に通えるのは、村に一人ぐらいしかおらず、毎日自転車で通学しとったそうです。その頃、自転車に乗る女性も村では二人しかおらなんだそうです。そういう時代でした。女学校卒業後は、農協に勤めました。
石動(いするぎ)に姉が3人おったんで、週末になるとそこに泊めてもらい、汽車で金沢に出て、大和百貨店に買い物に行ったりしとったようです。ボクはおふくろからそんなことは一言も聞かんかったけど、姉たちから「あんたのお母さんはこうやったよ」と聞かされていました。
父と出会う前、一度親に勧められるままお見合いして、結婚式を挙げたんです。ところが、式の真っ最中の2日目に、どうしても結婚がイヤで式をすっぽかして逃げ出したことがあった。籍に入る前で、結婚式を袖に振ったのが「負い目」になっとったようやね。おふくろは親の意向に素直に従わない、わがままな娘というか、それだけ自分の意志をはっきり持った女性やった。
【終戦を境に混乱した教育】
ボクたちは犀川にかかる桜橋の近くに住んどった。子供の頃は犀川でよく泳いだもんです。友達はアユやウグイをよく獲ったけど、ボクはそれがヘタやったから、いつも友達に魚をもらっとった(笑い)。そういう少年時代やったね。
ボクが新竪町小学校の4年生の夏、終戦になり、世の中が“ガラッ”と変わってしまった。戦前は金沢には第四師団が駐屯しとって軍都やったから、近所で四軒上手に陸軍の隊長さんらしい偉い人がおって、いつも兵隊が迎えに来とった。馬に乗って平和町近くの練兵場まで行っとった。それが終戦になると、“パッ” とおらんようになったよ。終戦を境に世の中の感じはもの凄く変わり、子供心にボクはショックを受けたですよ。
当時住んどった家は2階建てで4部屋あった。おふくろは自宅に四高生(現在の金沢大生)を4人下宿させとったです。彼らが召集され、出征する前に慰めてあげなあかんと言って、張り切って、どこからか肉を調達して来てスキヤキパーティをした。4人を「万歳、万歳」といって送り出しました。残念ながら全員戦死しました。
学校でも、戦後の教育は戦前と比べて、考えられんほど大きく変わったんです。ボクは3年生の時、「非国民」呼ばわりされちゃいました。理由は、履いとった長靴がボロボロになって、もう使えんようになったもんで、「長靴はいらん」言うて犀川の河原に捨てたんです。それを友達が先生に言いつけたもんで、「物を大切にせん」ちゅうことで「非国民」や言われて、講堂に立たされた思い出があります。
終戦を境に、一番残念だった思い出もあります。4年生の夏休み前まで戦争が続いとって、それまでの学校教育では教育勅語があり、国旗が掲揚され、校庭には二宮尊徳像がありました。夏休み中の宿題に「教育勅語をちゃんと覚えてこんとあかん」と言われて、ボクは一生懸命覚えた。夏休みが終わって二学期になり、勇んで登校したんです。教育勅語を完全に覚えたのは、クラスでボクを入れて5人だけやった。
そやけど、「民主主義の教育」ということで発表出来ず終わってしまい、それがとても残念やったね。それまでの教育内容もすっかり変わっとった。尊徳像も国旗も戦前のものは何もかも無くなり、教育勅語も謳わんようになった。それで校長室に行って「今まであったモンが無くなるのはおかしいやないか」と抗議したんです。真っ直ぐな心の持ち主の宮岸少年は、そうせざるを得なかった。
「民主主義教育」の元で、学級長を選ぶ選挙ではこんなことがあった。ボクはどうしても学級長になりたいもんで、鉛筆を3つに切って、みんなに「頼む」「頼む」っちゅうて手渡した。今でいうなら賄賂やね(大笑い)。特に女の子にバラまいてね。ボクはモテたわけではないけど、「結構、可愛かったんやないかな」(笑い)。
表面的には明るい宮岸少年だったが、終戦を境に激動、激変する社会での体験は、「少年ながらもその時は、精神的支柱が崩壊するような経験だったね。それ以来、生きる目的が分からずにいたところ、友達に誘われて聖公会に導かれることになりました」と振り返っている。
【「自殺」を考えるほどの試練】
父の死と終戦を境にボクの人生が大きく変わりました。その中で一番辛かったのが、小学校5年生から中学2年生の頃やったね。戦後の物不足の時代で、毎週土曜日になると、おふくろに代わって実家の福野まで行って、米をもらっとったんです。金沢から汽車に乗り、石動で降りて福野駅まで行き、そこからさらに八塚まで歩いて、だいたい2時間ほどかかってね。帰りは米をリュックサックにぎっしり詰め込んで、それを担いだ。小学生の時は3升ほど、中学生になると5升を担ぎ、両手にはもらった野菜をぶら下げてね。
おばあちゃんはボクをもの凄く可愛がってくれて、小遣いくれるから嬉しくて行っとったんです。でも、リュックサックを見るとあの頃を思い出して、今でも辛い気持ちになるね。ボクの人生の中で、苦しかった頃の一つやね。おふくろは自分で行きたくないこともあるし、周囲からいろんなことを言われるのがイヤやったもんでね。
もう一つ子供の頃にイヤやったんは、ボクは長男でしょ。親戚が集まった時に順番に座ると、小学生の小さいボクでも「お前は長男やから頑張らんとイカン」って言われたり、長男の場所に座らされるのが苦痛やったですね。父親を幼くして失った重荷を、こうした折に触れて感じる宮岸少年だった。
それが高じて、子供ながらに「もう自殺したい」と思う出来事が起こった。小学校5年生の時、いつものように母の実家に米をもらってきた帰り、闇米の摘発があったんです。津幡と森本の間あたりで列車が突然停車し、警察が乗り込んできた。全員汽車から降ろされ、並ばさせられてお米は全部没収やね。そん時ボクも引っかかったんです。警官は「坊や、悪いなあ」言うてリュックを取り上げてった。
明日から家族全員、食べる米がないと思うと、ボクは目の前が真っ暗になって途方に暮れてしまった。父の死後、親戚や周囲の人たちから、「あんたは家でただ一人の男だから、お母さんや妹をしっかり支えんといかんよ」といつも言われ、そのたびに「ハイ、分かりました」と応えてきたのに、その約束を果たすことが出来ない。
野菜だけぶら下げて、金沢駅の方へトボトボと帰ろうとした時、「もう何もかもイヤになってしまい、自殺しようと思って、ホームの先の方で動き出した汽車から飛び降りたんです。コロコロと土手を転げ落ちた。それを見て、駅の人がすぐに駆け付けて助けてくれた。幸いかすり傷程度で済みました」。
その直後、不思議なことが起きた。ボクを捕まえてリュックを持ち去った警官が近づいて来て、ボクのリュックを戻してくれるんです。助けてくれた駅員がその警官に話したのかどうか分からないが、「そん時ボクね、涙が出て、涙が出てどうしようもなかった。明日から食べる米がない、男として母と妹を食べさせなならんという重圧と、リュックが戻ってきた安堵感、それらがボクの心の中に入り混じり、ただただ“ありがとう、ありがとう”言うてね。泣きじゃくった経験があります」。11歳の少年には過酷過ぎる体験だった。他の同世代の子供たちには、味わいようもないこうした出来事が、師の心の糧として蓄積されていった。
若くして未亡人になった母親には、見合い話もあった。妻に先立たれたお医者さんとの再婚話で、香林坊の料亭でお見合いしたことがありました。そこにボクと同い年の少年が一人おった。連れ子やね。ボクはそれが絶対イヤで、猛反対したもんだから、再婚話は消えてしまいました。今にして思えば、あん時、母親が再婚しとったら、今頃ボクね、医者になっとったかもしれん(笑い)。
【友達に誘われて教会へ】
ボクがキリスト教と出会ったのは、小学校2年生の頃で、兼六園近くにあった川上幼稚園に行ったことがありました。そこは北陸学院の関係の幼稚園で、園長だったアメリカ人の女性にとても愛されました。
ところがある時、その園長が突然いなくなった。戦争が激しくなり、国に帰ったんです。ボクにとって、それがもの凄いショックで、「何故いなくなったんや」と他の先生に尋ねたら、「日本とアメリカが戦争しとるから、日本におられんようになって帰ったんや」と教えられ、とても失望したことを覚えています。
キリスト教との出会いで、もう一つ思い出があります。ヘレン・ケラーに会ったことやね。小学校6年生の時、昭和23年9月22日、2回目の来沢で、24日金沢市中央公民館の歓迎大会と講演会で、推薦された数人の男女児と一緒にボクも壇上に上がり、按手してもらった。体が大きくてね、ボクの頭に手を置いて祝福してくれた。やさしくて、川上幼稚園にいた時のアメリカの園長先生と同じ感触だった。『金沢市史 通史編3』にはヘレン・ケラーはこの時が2度目の金沢訪問で、湯涌温泉の白雲楼ホテルに3泊して9月25日離沢したと記されています。
新竪町小学校を卒業して、野田中学校に進みました。近所にY君という幼友達がいて、日曜学校に行こうと誘われました。Y君の家はお母さんが聖公会の信徒で、お父さんは関西学院大学の教授をしとった。けれど、ボクと同じような境遇で、お父さんが若くして亡くなった。彼は金沢大学付属小学校から付属中学校に行き、ものすごく優秀でした。
Y君とのエピソードでこんなことがあった。彼はとても動物がすきで、ウサギやニワトリを飼っとった。ある時、「宮岸君、もうすぐうちのニワトリが死ぬんやけど、いっしょに食べんか、ボク全部料理するから」と言い出すんです。「そんなもん、食べれんわいね」と言うたら、しばらくして肉だけ持ってきて、「一緒に食べよう」となりました。そん時、食べたかどうか、覚えていません。
また、学校近くの平和町に児童養護施設「享誠(きょうせい)塾」があり、そこに行くと、キャラメルやチョコレートがもらえるとY君が言うんで、「そんならボクも行く」と彼に付いていったんです。香林坊近くの南町には聖ヨハネ教会があり(現在は石引町)、そこでも日曜礼拝が終わるとお菓子をもらえた。ほやからボクが教会に行くようになったのは、初めはモノだったね。物質的なモノに惹かれて教会に行っとったわけです。それもちゃっかりと礼拝の終わり頃に行くんです。教会には直川(のうかわ)久之助という牧師さんがいて、ボクが片親だったこともあって、とても可愛がってくれ、ずっと面倒をみてくれました。その後、この直川先生から洗礼を受け、聖職者の道を勧められることになる。
ボクが日曜学校で非常に影響を受けたのは、Kさんという盲人でマッサージする先生がいて、その人は盲学校の副校長になった人ですが、その先生の影響で、ものすごく可愛がられて、礼拝で自由祈祷してくれたりした。
ボクの一番の友達で、Fさんという人、目があんまり見えない、虚弱で、一番胸が痛んだのは中学校の時、日曜学校に行く時にワザと道路の溝の方に連れて行ってね。ケガさせたことがあった。「宮岸君、なんてことするんや」とボクに殴りかかって来たりね、それが日曜学校からの友達やね。今はボクの生涯の友人ですね。そういう人の出会いとかね。
【父を越え、難関の泉丘高校に入学】
高校は泉丘高校と県立工業高校の2校を受験しました。人生の中で、一番嬉しかったことは何か言うたら、泉丘高校に入れたことですね。どうしてかというと、オヤジが石川県立金沢第二中学校(現在の錦丘高校)やった。ほやから、そのオヤジをどうしても越えたいとの願望がありました。それには金沢第一中学(現在の泉丘高校)しかないと思うた。当時は、通っている中学校で高校の入学試験を受けていたんです。それで泉丘と県立工業の応用化学を受けました。

担任の先生に「泉丘高校に行きたい」言うたら、先生は「宮岸君、泉丘は絶対受からんからやめとけ」と何度も何度も、ダメやダメやと言われた。そやけど、「どうしても受けたい、泉丘に行きたい」と言って、先生の反対を押し切った。最後に先生から「願書出すだけやぞ」と念を押されました。発表日に先生が泉丘高校に行って見てくれると、見事に受かっとった。その報を聞いて嬉しくて嬉しくて堪らず、泉丘まですっ飛んで行きました。「泉丘高校に入学出来たのは、くじ引きに当たったようなもん」と思っていました。
泉丘高校では、クラス全体がもの凄く勉強して、休み時間も勉強しとった。三年間はそんな時代やったね。朝、学校が近くになると、急に胃が痛くなった。どんなんか知らんけど。そんな時は、高校から犀川大橋を通り、大和の方までずっと歩いていくと、しばらくすると自然に治ってくる。そんなことが週に二回はあったね。ひどい時は三回も。Y君とは同じ泉丘高校だったから、学校生活はいつも彼と一緒で、ボクの代弁をしてくれたりした。ボクの後ろの席がY君だったから、試験の時など全部書いてもらったこともあり、もの凄く助けられた。Y君は卒業後、関西学院大学に進学し、地元の人と結婚して生涯を全うしました。ボクは高校時代に直川先生から洗礼を受け、ステパノという洗礼名を与えられました。ちなみにステパノとはキリスト教で最初に殉教した聖人です。
【大和百貨店での勤務】
泉丘高校を卒業してから、オヤジが大和百貨店の呉服部の部長をしていた関係で、大和に就職することになりました。当時は就職難でしたが、オヤジの関係で就職できたようなもんです。勤務成績はあんまり良くなかったんじゃないかな。朝寝坊して社員の出入り口じゃなく、玄関から入ってしまい支配人に叱られたこともあった。そのうち異動がかかり、関連会社の大和印刷の営業に回されました。二年間だけという約束で行ったんです。その会社には営業の人が4人おって、仕事は取引先を回って注文を取ってくることでした。ボクはどういうわけか、営業成績がトップだったんです。結局、関連会社に4年間勤め、異動になったんで、それを機に百貨店を退職しました。
第二章 聖職者として
【神学校へ、そして夏季勤務】
大和百貨店を辞めて、直川先生の推薦で、京都にある日本聖公会ウイリアム神学館に進学し、そこで3年間学びました。神学校では親しい同級生が出来ました。竹細工職人の家で育ったH君です。彼は中学、高校、大学とも夜間で学んだ苦学生で、ボクにとても影響を与えた男です。神学校を出て優秀な牧師として活躍しました。
神学校に在学中、生涯牧師としてやっていくかどうか、大きな試練がありました。それは神学校にいても「自分はもうやっていけない、伝道して牧師になれない」と強烈に感じたことがあったからです。何故かと言うと、授業に出てもラテン語がぜんぜん分らん。大学を出ていないので、学歴の問題もあった。H君も自身の出自に悩みがあって、ある時、彼と話していて、「ボクらはとてもやっていけん、福音を述べ伝えることはできない。だから一学期が済んで学校に戻ったら、一緒にやめよう」と二人で決めたんです。
それでボクは家庭のこともあるから、すぐに就職せんならんと思い、勤務しとった大和に電話して、「もう一回勤めさせてくれんか」と頼んだら、「君やったら営業で十分やっていけるから、分かった」と二つ返事で再就職が決まりました。
ところが、当時の指導教官から「やめるんやったら、いっぺん新宮の教会に行って実践してこい」と言われ、新宮の開拓伝道に出かけることになった。夏季勤務は神学校の夏の恒例行事で、一カ月間、訓練されます。
【伝道者として生きる決意】
勤務地は和歌山県新宮市で、そこで教会建設の資金のためにと、地元の信徒が作った『苦難の僕』という小冊子を販売するんです。ボクが新宮から田辺市に移ったら、本がとても売れて、三軒に一軒は買ってもらった。期間中、民家を借りて50人ほどの信徒を守りながら、朝6時に起きて礼拝をして伝道に出かける。販売の他、信徒の家を訪問したり、奉仕活動したり、貴重な経験でした。景勝地の瀞(どろ)八丁(はっちょう)にいるたった一人の信徒のために、荷物を担いて汗だくになりながら届けに行ったりもしました。
当時の思い出で最も凄かったのは、新宮を流れる熊野川が洪水になって、対岸の信徒さんのためにロウソクを届けたことです。指導教官が「宮岸君、私が向こう岸まで泳ぐから縄をしっかり持っとってくれ!」といって、命がけで泳いで渡り、届けたこともあった。
悲劇も起きた。ボクが伝道して親しくなった高校生が濁流にのみ込まれたんです。信徒と地元の方々が一緒になって、川岸を懸命に探したが,どうしても見つけられなっかた。仕方なく、ボクたちは彼の帽子と教科書だけで葬式をだしたんです。伝道しとった若い命が突然消えてしまい、とてもショックやった。彼の遺体はのちに収容されました。そんなこともあったけど、30日間の実践を通して、ぼくの気持ちの中に、牧師としてやっていけるとの確信が少しづつ強くなっていった。
夏季勤務を勤務を終えて学校に帰り、H君との約束通り、2人で一緒に辞めることを話しました。その時、佐々木主教からこう言われました。「ステンドグラスを見なさい。いろいろな色で十字架やキリスト像を描いている。宮岸君はどう思うかわからんが、その一片になりなさい。例えばグリーンならグリーン、赤なら赤に、そういう色になりなさい」といわれたんです。この言葉は、ボクが聖職者としての生涯を貫き通した言葉になり、改めて聖職者として生きていこうと思った。この言葉は誰に会っても話をすることです。夏季勤務を通して「ボクは天の召命を受けたんです」。そこでH君に「ボクはキリストの一片になるために、どこまで続くかわからんけどやりたい」と告げると、H君も「ほうか、そんならワシもそうする」ゆうて神学校に残ったんです。(大笑い)
【新天地・加悦へ、そして結婚】
昭和37年3月、京都のウイリアム神学館を卒業したボクは、司祭になり、初めての赴任地は府内丹後地方の与謝野町にある、加悦(かや)聖三一教会になった。この教会は、加悦と宮津、四辻伝道所の3カ所を管理しとったが、しばらく司祭が不在で、ボクは伝道師として着任しました。その後、執事になり、司祭になった。
加悦地方は古くからの丹後ちりめんの産地で、地域を横断するちりめん街道は、道路の両側に昭和のたたずまいを残し、重要伝統的建造物群保存地区に指定されている。街道を散策すると、商家や医院、銀行などかつての町の賑わいを伝える建物が多く残っており、「ガチャ、ガチャ」と機を織る音の聞こえてくるのどかなところでした。
加悦では、ボクは黒い司祭の服装のキャソックを着て、十字架をぶら下げて聖書を持って日曜学校の案内パンフを配っとったんです。ところがある時、教会に来とった女性信徒から突然、「先生は羊の装いをした狼や」ときつい言葉を投げつけられた。そんなこと、これまで言われたこともなかったんで、ビックリして『これはえらいこっちゃ』思うてね、身を飾らないで、地のままでやろう思うて、黒の礼服を着るのは礼拝の時だけにして、普通の恰好をしていました。
その女性の言葉がどうしても気にかかり、後日、謝りに行かんならんと思って会いに行ったら、彼女は精神疾患で、もう病院の精神科に入院しとった。その時初めて、精神を病んどる人は人を見抜く力があるなぁと思うてね。聖書に出てくるイエス様の弟子たちが、病んでいる人を見抜いて癒していく姿が思い出された。そういうこともあって、ボクは伝道する時には、たとえ羊の装いをした狼だと言われても、ステンドグラスの一片になりきろうと牧会に励みました。それでボクは病人や施設に入っている年配者、社会的に孤立している人などに触れあってきました。
師にとって、加悦は人生の大きな転換点となった。最良の伴侶、儀子(よしこ)さんと結婚、27歳の時だった。そして長女るつ子と長男真の2人の子供に恵まれた。結婚について師は、「ボクにとって結婚は、人生の中で一番うれしいことでしたね。もし家内がいなかったら今日、こうしておれません」と話されている。
【妻と歩んだ二人三脚】
妻の儀子さんは昭和6年11月4日、三重県四日市市の生まれで、牧師の養女として育った。というのは、彼女には結納を交わした婚約者がいた。相手の方は野球大好きのスポーツマンだったが、結核で喀血して、その後亡くなった。それが原因で儀子さんはとても落ち込んで、しばらく教会巡りをしとったんです。その時、伊勢市にあった聖公会の岡島七郎先生に出会い、その元で働くようになりました。ちょうど先生には子供がいなかったんで、先生の養女になって籍に入り、教会で一緒に生活しとったんですね。

そんな矢先、とある主教の葬儀の場で、ボクは上司の牧師と一緒に参列し、そこに家内がいたんです。ボクたちの馴れ初めは、ボクが一方的に一目惚れしたということなんです。それで主教に頼んで仲を取り持ってもらおうとしたり、結婚できなかったら牧師やめるくらいの言い方をしてね。あらゆる手を使ってプロポーズし、その努力が実って結婚にこぎ付けました。家内に直接言うたんじゃなく、周りの人を通して進めてもらった。そやからね、二人で会っていても恋愛感情がなく、といって見合いとも違い、変な感じやった。
家内の旧姓は岡島ですが、生まれながらの姓は山崎でした。前述のように、彼女の青春時代はかなり大変だったようで、話を聞くと、プロポーズもかなり申し込まれたようです。そういう魅力があったんでしょうね。そこへボクが割り込んだわけ。ボクがプロポーズした時には、すでに約束した男性がおったんや。相手は学校の先生で、伊勢市近くの海岸にらい病の施設があり、そこで一生懸命、社会奉仕しとったようです。家内はその先生のプロポーズを断って、ボクのところに来てくれました。いろいろあるわね。岡島牧師は相手の男性には8人兄弟がいて、そんな環境で結婚してもうまくいかんと考えて、結婚には反対したようです。
ボクと結婚して、家内が幼稚園に関わるようになり、とても良い働きをしてくれた。例えば、町内の運動会では、他の幼稚園も来てる中で、たった40人の子供たちで、みんなから注目されるような出し物を準備しました。どう考えたか知らんけど、風船あるでしょう。風船にガスを入れ、大きな箱にそれを一杯詰め込んで、音楽が終わったとたん、それに合わせて、空に向かって風船を一斉に飛ばしたんです。そのカラフルで見事な演出がいっぺんに評判になってね、それで入園希望が増えて、園児の数が90人ほどに膨れ上がりました。園児が増えたのは、家内の力がとても大きかった。
ボクにとって家内は、人間愛に満ち、母親でもあり、同時に立派な指導者でした。絶対必要な人ですね。いろいろ指図はしなくても、そこに居るだけでボクの伝えたい事、言いたい事がみんな伝わっているように感じます。それだけ意志の疎通が出来ていました。だから帰っていくところは、家内のところだけですね。幼稚園の行事なども、全部自分で立案してやってくれる。ボクの方からこうして、ああしてと言ったことはほとんどないです。物事をテキパキとこなせるのは、二十歳の頃から辛酸を舐めてきたことも関係があるんでしょうね。
【金沢聖ヨハネ教会でのあゆみ】
ボクは七年間、加悦を拠点に布教活動に専念した後、昭和44年、家内と子供たちを連れて金沢に来て、金沢聖ヨハネ教会に奉職しました。「宮岸君、悪いけど金沢に行ってくれんか。預言者は故郷で尊ばれず、と聖書にあるが、三カ月だけ行って欲しい」と頼まれたんです。聖書に「イエス様は故郷では受け入れられなかった」とありますが、金沢ではボクもそうでした。礼拝するでしょう。すると参列者は半分あっち向いてましたもんね。ボクの小さい頃を良く知っとる信徒さんばかりだったからね(笑い)。
金沢では三カ月どころか、結局60歳で辞めるまでずっと奉職することになりました。長くなった理由は、教会の裏に聖ヨハネ乳児保育園を建てたんです。信徒の一人に石川県で初の女性県会議員になった駒井志づ子さんに園長として立ってもらい、保育園の建物を建てたんです。ここからボクの社会福祉の仕事が始まるわけです。
当初、ボクの教会での活動の中心は、礼拝・日曜学校・聖書研究会と老人の福祉活動ですね。訪問することが主でしたね。それはその後、社会福祉に全部つながっていますね。その頃の思い出をいくつか話します。
ある日、直川先生が教会に連れてきて、面倒をみて自立させた信徒がいるんです。その人は長野県松本市の呉服屋の店主だった人で、家がつぶれて、破産して一人になって金沢駅でウロウロしとったところを直川先生がその人の人生を全部聞いていたんです。その後、信徒の人が面倒をみました。直川先生が「品のある人がおると思ったのかな」、いつも着物を着て、シャキッとした人でした。着物姿で礼拝にも出ていた。鳴和の裏手の二間だけの家に一人で住んでいた。55、6歳の時に出会い、洗礼を授けてクリスチャンにしました。教会の二階に住まわせて、家を見つけて、和菓子屋さんへの就職を世話して、彼はスクーターに乗って配達に頑張っていた。
訪問が中心の伝道を金沢でしとったんです。そのうちに学生たちも集まるようになり、育っていったんですね。教会で待っとるんやなくて、家庭訪問が中心ですね。それがずっとですね。うちの教会の二階には、青年がいつも二人ぐらい居候しとったですね。彼らが育ってみんな社会に出ていったですね。金沢大学や金沢美術工芸大学の学生さんもいましたね。
そんな学生の中に、T君がいます。福井県のある市長の息子で、聖公会の関係でね。高校時代に登校拒否で学校に行かんようになって、市長さんが困って、息子をなんとかしてくれんかと言われて、うちで預かっていました。早稲田大学に進学して、同大の大学院を出て、東京で出版社を起業し、小さいながらも好きな本を出しています。
もっとボクの記憶に残るのは、社会が乱れていた頃、片町へ飲みに行った帰りに、片町の交差点で手を振っている女の子がいて、その子は信者さんの娘や。高校生で、星稜高校を退学になった。県内の高校は行くところがないでしょう。それで富山県の高岡市に女子高があってそこに頼みこんで入れてもらって、卒業できた。今はとても良い奥さんになって、息子もちゃんとしとってね。良かったです。お母さんは小松にいるんやけど、とても感謝されました。
ボクは信仰的なことや聖書の話はあんまりせんと、短いお祈りはしたんです。聖公会の祈りは長く受け継がれている祈祷書が50余りあるんです。その人に必要な祈りがチャンとあるんですね。病人とか危篤の人とか結婚式の祈りとか、その人に必要な公的な祈りが決まっています。それとは別に、個人的な祈りは私祷です。それは自由祈祷ですね。公祷だけしとったらいいという牧師もいますが、公祷を補うために自由祈祷があります。二つの祈祷が必要なんですね。ボクは公祷だけでは足りないと思っています。
牧師さんにはハイチャーチとローチャーチがあって、ハイチャーチは儀式を重んじる牧師さんと、カトリックのようにね。それと自由祈祷を中心にいくローチャーチの牧師さんと二派あるんです。そん中から主教が選ばれるんです。主教になるのは並大抵でなくて、被選主教になるには主教選挙で選ばれることが必要で、それが決まるまではお祈りしながら続けていくんです。
【福祉事業拡大への落とし穴】
積極的に次から次へと福祉事業に着手し、保育園と養護施設を設立。3件の福祉施設を経営し、ほかに10件の理事をするまでに事業が拡がった。
どんな時期かというと、牧師が教会をほっぽり出してね、主教が先頭になって、牧師のほとんどがこの世の事業に邁進したんです。幼稚園に学校、社会福祉事業、老人施設などに7割の牧師が関わっていった時代があるんです。
私は福祉事業では京都教区と関わりを持ってやってきました。理事(役員)だけでも15件ぐらいしとったですね。一番大きいのが聖ヨハネ会やね。それは乳児保育園、双葉保育園やね。最後が能登の「聖ヨハネ会 しお子どもの家」で、理事長しとったんですね。金沢では野々市の和光保育園、そこの園長もしたことがあります。それに津幡の向陽台保育園の理事長もしとったです。ボクは、日本聖公会の老人ホームで神奈川県の聖ベタニアホームの設立者の一人にもなっています。ここは日本聖公会の福祉施設の一つです。
その時代の時流(バブル経済)もあったと思いますが、福祉事業を拡大する中で借金がかさんでいったのです。主な借金は能登に作った「しお子どもの家」ですが、その前に双葉保育園がありますし、聖ヨハネ乳児園で借り入れしたのがあります。ボクは生活がこの世的で、いろんな付き合いもあり、よく飲みに出て歩いたもんですから、半分は自分で贅沢した部分やないかと思いますね。今の気持ちは、全部自分の贅沢のもんやと思ってます。
それが教会委員会で問題になって、借金は全額返してもらわんとダメやというふうになって、私的に使われたんやないかとなって、教会委員会が管区に訴えたんです。それを解決せんならん。うちの教会の二人のメンバーは、初めからボクが教会に来るのを反対しとった人たちやった。それで訴えようとした。日本聖公会の土地は一つの財団に管理させていた。そこへ訴えた。そこの理事長がY主教やったんです。主教とボクは連帯責任ですね。Y主教は全国の財団を管理する聖ヨハネ財団の理事長やった。
60歳で退職しました。退職の理由は、自己資金は自分で寄付せんならんのですね。それは法人がキチッと返すもんやったんですけど、ボク一人の責任になっとるわけです。悔やまれることが一つあったんです。それは、当時、教会の電気関係の事業を一手に請け負ってくれていたY県議から「自由に使ってくれ」と言ってお金を渡された。そういうお金はものすごい怖いもんでね。自分のお金でないんやけど、何も苦労しないで儲かったような感じでしたから、そうとう無断に使ったですね。そのような借金はボクと家内の給料の中から法人に寄付して返すという形になり、退職することになったんです。その借金を全部返済したのが75歳ですよ。
管区では主教が7人で、それを聞いて、自分は辞める、後は頼むゆうて、京都教区の常置委員、司祭3人と信徒3人の6人の人で、その中にH女学院の理事長もいれば、京都のSという教授もいれば、選挙で選ばれた人、司祭が3人で中心の人たちが主教を守ろうということで守ったんです。
その時にY主教からボクも呼ばれて、「宮岸君も相当借金がある。一緒に退職しよう。自分は神戸の学院の教授としていく。それで借金の一部は本部が返してくれたんです。それでも足りない分はボクが返していくことになったんです。
【借金の返済での苦労と反省】
当然のことだが、そのため莫大な借金を抱えることになり、その責任を負って牧会者を辞任した。人一倍責任感の強い師は、借金返済のためアルバイトに出て、朝はごみ収集の会社で、夜はサウナ風呂の掃除と懸命に働いた。
「ごみ収集は朝が早く、三時に家を出て六時頃に終わる。クリスマスの時、道端で涙したこともありました。教会の人がキャロルを歌っているのが聞こえてきて、去年まで一緒に歌っていた『聖しこの夜』を道の向こうの教会で歌っている。ボクはこっちでごみを収集している。「涙が込み上げて仕方なかったね。信徒のみなさんと一緒にクリスマスをお祝い出来ないことが申し訳なくてね」。こうした苦労を重ねながら、奥さんと二人で返済に取り組み、多額の借金をすべて完納し終わったのは75歳だった。
ボクの自論は、牧師は本来、基本的に借金してはいかんです。与えられたものだけで感謝して、その日を過ごす生き方が一番正しい。聖書一冊持って伝道するのが本来あるべき姿だと思います。ですから、ボクが一番せんなんことは、日曜学校と伝道、それと老人や病人、そして一人で寂しく生活しとる人を訪問することやね。パンフレット持って、按手して、手を置いてお祈りすることです。
ほやけど、そこに家族がいたりすると経済的なものが発生してね。この世の流れの中で、幼稚園とか保育園、養護施設とか必要とする時に牧師が関わっていく。それらの経営は、今日では牧師から信徒の方に移っています。信徒が経営の中心になってきた。それはとても良いことだと思います。牧師は教会だけ担当すべきです。ボクの信ずる神様は時代の中で働く神様です。そういうふうに思うてるんです。
第三章 新たな出会い、ブライダル宣教とエキュメニカル運動
【新たな出会い(再会)】
話は少し遡るが、昭和46年(1971年)秋、その後の師の信仰生活でかけがえのない一人の青年と出会う。当時金沢大学理学部の学生で真理探究に熱心だった三國進一郎君だ。彼は聖ヨハネ教会の一室を借りて40日間寝泊まりし、ボクは彼にキリストとの生き方や聖公会の教理を教え、その代わり一日に1時間だけ、彼の学んだ統一原理や聖書解説を聞くことになった。彼に対しては、聖職者として聖公会に入れて、後々は聖公会を支える人材に育てたいとの思いがあった。
三國さんと出会った頃、教会には同じ金沢大生の大川君もいました。彼も好青年で、三國さんよりも一歳年上で、その後、聖公会に残ってくれた。ボクみたいに夜になると飲みに行くということはなかった。お酒は好きやったけどね。
三國さんは、その後、他教会の海外宣教師として南米のスリナムに派遣され、再会したのは2001年(平成13年)5月でした。その年、共同でユニバーサル福音教会を設立し、3年後の年末に、一緒にイエス様の戴冠式でイスラエルを訪問することになります。三國さんはマイアミビーチでペンテコステ派(福音教会)の牧師から全身洗礼を受け、洗礼名をミカエルとし御國新一との牧師名を持っていた。
聖公会は、プロテスタントの中で和解をさせる教会だと思っていたんですけど、ちょっと違うなと思うこともあります。しかしカトリックともプロテスタントとも超教派的に和解に努力する。聖公会の基本的なことは、建物が教会じゃなくて、その人の人格自身が教会ですから。それはイエスによって支配されてる人間であるちゅうことです。それがちょっとチョロチョロとね、この世の方に行ったりしていろんな色合いになるんやけど、それをまた一つにするのが教会であり、それを束ねているのが主教なんですね。けど、カトリックのようにポープ(教皇)はいない。そういう組織です。
【ユニバーサル福音教会の設立】
2001年5月に設立したユニバーサル福音教会は単立教会で、牧師達が運営しています。私と日本基督教団の三田先生と御國師、三馬の修道院で司祭をしていたチプリアーノ神父の4人で、ボクが中心になってやっとった。後に相沢牧師が加わった。彼は離婚して教区から出て、面倒見てくれと言われて、この5人でユニバーサル福音教会を作ったんです。ユニバーサル福音教会では教会の綱憲を定め基本方針と教会法規を採択し、教派に関わらず聖書とキリスト教の神学にある程度精通し宣教経験を3年以上有するもので牧師3名以上の推薦を得たものを司祭が牧師に認定した。今までに20数名の各派の牧師がユニバーサル福音教会に加わった。
そこに外国人も加わって、聖公会には特志伝道師という制度があり、今はないですけど。その人は教会がないために牧師に代わって礼拝をしている。そのような敬虔な信徒は外国人も含めてチャペルでの特志伝道師として認定した。もちろん結婚式の司式は、特志伝道師も出来るんです。
もう一つ、チプリアーノ神父や三田先生、相沢先生は聖公会のブライダルの司祭ですが、彼らとキリスト教ブライダル協議会を創ったのが最初で、御國師と出会って、単立のエキュメニカルな教会を創ったのが流れですね。
キリスト教各教派間の和解と一致だけでなく、他宗教との対話と協調にも努力し、神の愛による世界平和実現の祈りと奉仕活動を目標と定めたんです。愛の基本は家庭です。結婚は主が最初に人を造った時から神様が与えた祝福なんです。不思議なことに日本では葬儀の9割以上が仏式で行われるんですが、結婚式は7割ほどがチャペルで行われるんです。ウエディングドレスを着てのファッションではなく、キリストの愛により讃美歌を歌い、聖書を拝読し、祈りと主の祝福で行おうというのがユニバーサル福音教会設立の主目的なんです。
組織を創って、結婚の尊さ、家庭の大切さを強調して、設立当時はブライダルがブームになっており、チャペルで式を挙げるカップルが多かった。家庭での神様の大切さ、信仰の大切さを説いた。中でもコリント人への第一の手紙の「信仰と希望と愛」を引用し、最も大切なのは愛である、と伝えてきました。信仰はキリスト教だけにかかわらず、心の中で望むものを信じて、そのために努力する、神にある望みを忘れない、それも愛に基づいている。結婚式のメッセージとして生きていくことであり、家庭でも大切である。超教派的な、どの宗教でも関わることであるし、愛し合う事も出来、共に歩むことも出来る。ボクはキリスト教会の中で育ったわけだから、それを基盤にしとるわけ。他の人は仏教などとの関係で信仰している。中には無神論の人もいる。信仰はないけど、目に見える人を愛するとか、それだけで人生を送る人もいる。それを含めて、宇宙全体や。
それは聖公会の長い歴史の中で育まれた中にあるんやね。ローマカトリックがあって、十字軍があって、英国が攻められて、最後的にプロテスタントという良い教派を創ったとボクは思うとる。
聖公会はカトリックが持っとった迷信的なところは全部排除したわけ。ルターは違う。聖書のみ、信仰のみで進んだ。その点聖公会は長い伝統から伝わっているものを大切にし、修道院を残した。キリスト教はいろんな教派がたくさんあるけれど、自分が身を置くとするならば、聖公会やと思たんです。
カトリックのように司祭を重んじ、儀式を重んじながら礼拝をするハイチャーチとそれから私のように自由に自分の責任において牧会する、辞める基準はその人に問題が起こるとか、離婚するとか、社会的に制裁を受けるとか、辞める基準があるんです。それに適応する時に辞める。
牧師が最も辞める率が多いのが、好きな人が出来た時。これは多いですよ。人間やなと思うてね。牧師全体の課題やと思うわ。最後まで全うするのはね。
聖公会の手帖には、名簿の中に懲戒された人が載るんです。信徒との間で不倫して家族から訴えられて、その人を排除する裁判をして、それまで教会で裁判があることは全く知らなんだ。休職した人や懲罰を受けて永遠剥奪の人もいる。
ボクがユニバーサル福音教会の設立を確固たるものにしたのは、宗教新聞に毎年、年頭の挨拶文を載せていた。それで管区から何故統一教会が関係する新聞にこういう文章を出すんや、と電話がかかってきた。そん時ボクはカチッと思たんや、そういう偏見に立ち向かわんならんなと思うとる。
御國師に結婚式場からいろいろ任せた理由は、お金が入って来る。ボクはその管理がうまく出来ない。それで任せて、会計上はキチッとなっとる。二人合わせて二十数年で数千組やった。

イスラエル聖地「金のドーム」をバックに宮岸司祭と御國師
【イエス・キリストの戴冠式でイスラエルへ】
2004年12月17日、イエス・キリストの戴冠式でオランダ経由でイスラエルに行きました。その趣旨はイエス様がこの地に誕生されて、当時のユダヤ教の人たちに油を注がれた者として受け入れられたならば、ユダヤの王として来られた方だと、ところが、パリサイ人や指導者が不信して、ある意味では悪鬼の頭のような扱いを受けて十字架で亡くなられた。亡くなって罪を背負い、贖罪としてのイエス様は受け入れ られるけど、本来信仰があったならばユダヤの王として神のみみ旨をその時に成就していたら再び来る必要もなかったというのが、主催団体;世界超宗教平和会(ACLC)の信ずるところなんですね。御國師とイスラエルに行った。アメリカの牧師たちがそれを支持して、イエス様の十字架は本来の神様の一義的なみ心ではなかった、それを外して、イエス様に神様からの王冠を被せる戴冠式を行うというのが主旨だったんです。それで特にアメリカの牧師たちが立ち上がって賛同して大会をやったわけです。
ボクが確信を持ったのは、英国の司祭がおった。それともう一人アメリカの司祭がおった。それが加わってた。聖公会もこの大会に加わっているんやなと思うたんです。これは画期的な、神のみ旨による大会だなと、感動の期間でしたね。当時は国際的には厳しい、そんな大会が開けるような雰囲気じゃなかったんですね。イスラエルに入る時もセキュリティで4時間もかかるほど厳しかったですね。
そんな中でもパレスチナにも入れましたしね。イエスの生誕教会、イスラエルは近代国家、それでバスで行くでしょ、さらにバスを降りて別のバスに乗り換えて、直接に教会に行くだけ。ガイドの人は外の売り物は絶対に買ってはイカン言うてね。
その生誕教会に行って驚いたことは、教会を守っている人にはカトリックの神父もいるんです。その横にはカトリックの教会も立っとんです。だけど、そこの規範を守っとるのが、そこの国の兵隊ですね。教会はパレスチナ自治区に半分はある。だからイスラエル側から入って、向こう側に出たらパレスチナだった記憶がありますね。ほやけどね。大変な感じやったね。パレスチナ自治区に入ると、その裏側が壁になっていて、その向こう側はイスラエルで、異様な感じやったね。
戴冠式の主催は世界超宗教平和会議で、いろんな教派の人たちが来てました。アラブの人も、インドネシアのイスラム教最大会派の指導者、ワヒド元大統領も代表で来ていました。5万人大会が開かれました。エルサレムの街中を、肩からタスキをかけて平和行進した。雨が降ってきて二列に並んでね。その時、ボクね、滑って転んだんです。その時、ボクの頭を持って助けてくれた女性がおったんです。彼女はウチの家内をよく知っていて、礼拝堂の花を土曜日に買っとった。家内が注文しとったんですね。
イスラエルは丘が多くて、坂も多い。だから行進も階段があるところを歩いた。そこで滑って一回転して無事だった。
ユダヤの聖地の嘆きの壁でお祈りし、その横にある洞穴みたいなところはイエス様が最後の晩餐をした場所として残っています。その上に金のドームがあって、旧約聖書に出てくるアブラハムがイサクを献祭した場所でもあり、イスラム教徒にとってはマホメットが昇天した場所でもあるんですね。だから、そういう聖地があり、イエス様が最後の晩餐をした場所でもあり、とても印象的でした。旧市内全部を2時間ほど行進しましたね。大会もあったしね。他宗教のいろんな聖職者がたくさんいました。
【変革期を迎えている聖公会】
参加して聖公会はダメやと思うた。この組織ではボクのような生き方をしとったら聖公会はつぶれると思ってた。高度経済成長の時代の中ですから、もうあかんなと思うた。それでも聖公会は滅びないとも思うた。ちゅうのは三分の一ぐらいの牧師は信者さんから捧げられたわずかな献金で生計を立てていた。牧師の給料はそん時は決まってなかったですから。その牧師の牧会力によって給料が決まるわけです。黒い服(キャソック)を着て、十字架ぶら下げて、黒い服は裏返しして、家族も貧しい生活をしながら2、30人の教会を守っとる牧師が全国に三分の一ぐらいいたですよ。その人たちによって聖公会が救われたんです。それと立教大学などの学校や聖路加国際病院などのチャプレンとして献身的に働く人たちが聖公会という組織を守ったと思うんです。
だから、選挙の時、そういう人が主教になるんです。Y主教の時代から始まってね、改革していかんならんと、派手にやってた主教が70歳で退職する。主教選挙は代議員が集まって信徒の票が三分の二、聖職者の票が三分の一、それがピタッと当てはまるまで、主教を選ぶことが出来ない。今もそうですが、そういう人が主教に選ばれてきた。我々はどんな主教が選ばれても従ってやっていかんとあかん。選ばれた主教によっては全部人事異動する主教もいれば、今の体制を守らなくちゃならないという主教もいたんですが、だいたいその時は全部人事異動でしたね。例えていうなら、有名な牧師の信徒などを作らないシステムになっとる。
カトリックの法王を選ぶ選挙と同じです。祈りながら選んでいきます。それで一人決まらんと言う時があるんです。ボクが一緒にいたY主教の時がそうでした。ボクの一票で決まった。Y主教に投票せんほうがよかったかもしれん。ボク以外の牧師は全部人事異動したです。自分に反対する人はことごとく地方に異動させた。人間的な弱さ、世渡りが出てくるですね。当時は世俗的な人たちが選ばれた。推薦したり、応援している牧師はみんな世俗的なタイプでした。今はいいですけどね。
近年、聖公会が女性の司祭を作ったんです。特にアメリカで女性の司祭が選ばれるようになり、日本でもそうなり、ボクは反対しとったです。全国で80人ほどの牧師が反対して。ボクの考えの中では、修道院の長になるとかね。補助する執事になるのは構わんけどね。司祭になってミサを仕切るのは反対です。
理由は聖書には男性は神の栄光、女性はそれを補佐する立場、あくまでも聖書的な視点からです。世界的には女性も選ばれる時代になってきました。その反対しとった女性の司祭が金沢に来るとは、ちょっとご縁やね、これ。ほんでもね、会ったことはあるんですよ。
その女性が金沢大学を卒業した時にウチの聖ヨハネ教会の信者になったです。その時の司祭というのが今のK主教ですね。K師(当時司祭)がボクの後に、聖ヨハネ教会の牧師として赴任して来た。その時にその女性が信者になったんです。
勿論、ボクは男性と女性は平等だと思います。かつて女性が不当に扱われていた時代あったのは事実で女性が平等に社会の中で活躍すべきだと思います。しかし、聖書にあるように男性と女性の役割の違いはあると思います。聖書に書かれていることは意味があることです。それを否定することには反対です。
K主教は神学生の頃に私が面倒みたんですよ。K師は、金沢の教会はとても続かんゆうて、二年ほどで辞めさせてくれゆうて。ウチの聖ヨハネ教会は牧師が続かんゆうて辞めていった。何故かゆうと、司祭みたい、牧師みたいな信徒がたくさんいる。こんな教会はとても続かんゆうて、ボクが辞めてから5人ほど変わったです。

第四章 座右の銘「信仰・希望・愛」
宮岸師の座右の銘は「信仰・希望・愛」、これは新約聖書の「コリント人への第1の手紙13章13節」にある聖句の一説です。この三つはいつまでも残り、その中で最も大切なのは愛です、と説いています。人生で愛に悩んだ時、家庭問題、事業でいろいろ困難な状況になった時、信仰が大きく影響している。それはもう決定的やね。イエス様との出会いとか、神様との出会いなど、さらに希望を持つことの大切さなどね。
師は実のところお酒は飲めないのですが、よく片町の飲み屋に通った。そこで女性たちと知り合い、ヒザを突き合わせて彼女たちの話し相手になり、接客の苦労話や悩み事などをとことん聞いて、彼女たちの心の支えとなってきた。気さくで親しみやすい姿に、日中、片町界隈を歩いていると、女性たちから「先生、先生」と言って親しげに声を掛けられることも少なくなかった。
また、師は右であろうと左であろうとイデオロギーにとらわれず、友情を結び、彼らをやさしく包み込む広い懐の持ち主でもあった。学生運動に挫折し精神的に崩壊した学生たちと関わり、彼らを教会に泊めて伝道に努めたことも多々あった。それは、師自身が小学校時代に精神的空白を経験したので、彼らの気持ちがよく分かるからだという。師の生涯は身をもって、キリストの示した愛に取り組み、それを実践してきた軌跡だった。
そして師がいつも目標とし愛唱した聖句が次の聖句である。
イエスは言われた。「心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。」これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。「隣人を自分のように愛しなさい。」律法全体と預言者は、この2つの掟に基づいている。(マタイによる福音書第22章37節~40節)
【追 記】
師の娘さんによると、師は手先がとても器用で、しかもアイディアマンだったという。数あるエピソードの中から幾つか紹介しよう。市内の芝寿司の店頭には、年間を通して、アンで包んだ美味しそうなおはぎが並んでいる。同店の人気商品「おはぎのマリちゃん」だ。甘さが控えめで、最高級の十勝小豆を仕込むなど、こだわりのおはぎで、これは師が考案したともいわれている。また、足袋を参考に、指の分かれたくつ下も発案し、商品化されている。一方、クリスマスになると金沢聖ヨハネ教会の玄関に大きなもみの木があり、師は奉職中毎年その木の枝を切りアドベントリースを造り飾った。信徒たちは、そのデコレーションを毎年、楽しみにしていた。
<宮岸進師・履歴年譜>
1935年(昭和10年)7月15日 誕生日
1954年(昭和29年)3月 県立泉丘高校卒業
1954年(昭和29年)4月 株式会社大和百貨店本店勤務
1958年(昭和33年)3月 同百貨店退職
1958年(昭和33年)4月 ウイリアムス神学館入学(京都)
1961年(昭和36年)3月 同神学館を卒業
1962年(昭和37年)4月 加悦聖三一教会奉職、加悦聖三一幼稚園長代理
1969年(昭和44年)3月 同教会、幼稚園を退職
1969年(昭和44年)4月 金沢聖ヨハネ教会奉職
1970年(昭和45年)11月 社会福祉法人聖ヨハネ会理事長に就任
1978年(昭和53年)4月 社会福祉法人和光保育園長として勤務
1980年(昭和55年)3月 社会福祉法人和光保育園退職
1982年(昭和57年)4月 養護施設しお子どもの家施設長就任
1991年 ~1995年 金沢聖ヨハネ教会牧師等退職
1998年 ~2015年
2001年5月~
全国ブライダル協議会に参加
チャペル司祭として約3000以上の結婚式を司式
ユニバーサル福音教会 設立代表牧師奉職
(エキュメニカル派単立教会として後にキリスト教年鑑に登録)
2004年12月 御國師と共にイスラエル訪問(超教派の大会参加)
第8回総会セミナー
記念スピーチ
宮原亨
(元日本基督教団正教師)
説教概要

(1)挨拶と御礼、車窓で見た北陸、金沢の印象。
「北陸はキリスト教不毛の地」と聞いていました。
キリスト教年鑑で調べると、石川県の教会の総数は65、金沢市は30。石川県に10以上の教会のある市町村は金沢だけ。
これに比べると千葉県の教会の総数は370。千葉市は60、柏市27、船橋市24、松戸市23、市川・浦安市25、市原市20、10以上の教会を有する市町村は10市。
石川県の教会数は千葉県の約六分の一であることからも宣教不毛の地であることが証明される。
このような宣教困難の地での皆様の日ごろの宣教の苦労に心からの敬意をはらいます。何故宣教不毛の地になったのか?理由は北陸地方が一向宗の強い所だからだと推察いたします。
戦国末期から江戸時代にかけて、日本ではキリシタン禁教のため、神道・仏教が国策として利用された。これが明治以降もキリスト教宣教の大きな障害になったことは間違いない。市民生活の冠婚葬祭を隅々まで神道・仏教が牛耳ったため、キリスト教が市民社会に入る余地がなく、やむなくキリスト教は近代思想という形で、大学で講義されるものとして存在するしかなかった。これが日本のキリスト教が学問的キリスト教となった理由です。(「石地に撒かれた種」:マタイ4/5)
特に北陸地方では、一向宗による、市民社会の支配が一層強いものであったため、このような結果となったと思われます。(「道端に撒かれた種」マタイ4/4)
(2)このような状況下にあるからといって暗くなることはありません。
本日のテキストはイエス様が十字架に掛かり、弟子たちが絶望の淵に落ちていた時に起こった出来事を伝えています。「三人の女が日曜の朝早く墓参りに出かけたら、重しに使われていた大きな墓石は取り除かれ、墓の中はカラであった。中に天使がおり『あの方は復活なさって、ここにはおられない。…あの方はあなた方より先にガリラヤに行かれる。…そこでお目にかかれる』と言った。女たちは恐怖に震え上がり、逃げ帰った。何も言えなかった」とある。
マタイ28/9を見ると、この時イエスが現れて「おはよう」と言われたとある。
実はこの「おはよう」はギリシャ語のカイレーテ(カイロ―:喜ぶの命令形)、喜んでいなさいと言う言葉。
本当は、「悲しんでいないで喜び、喜べ」と言ったのである。皆さん喜んでいますか。それとも、宣教が上手くいかず、悲しみに沈んでいますか。悲しんでいたら宣教は絶対上手くいきません。だから何があっても喜んでいる必要があるのです。「いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことでも感謝しなさい」(Ⅰテサ5/16)と言われる所以です。
悲観的にならず、超楽観的であれと教えています。神様が救おうとされているのだから、必ず救いは成就するという確信である。

(3)本日のテーマは「墓石が動いた」である。
イエスを蓋していた巨石が取り除かれたというメッセージである。日本のキリスト教界内部を見ると宣教不振で閉鎖に追い詰められそうな教会が数多くある。
2030年には教勢が半減すると案じられている。しかし、それ以上に深刻なのが神道、仏教である。戦後の産業振興に伴う村社会の崩壊は檀家、氏子を激減させ、世俗化と少子化が追い打ちをかけている。永く無宗教で生きてきた現代人の中に、死んだ時の葬儀を願わない人が増えており、「直葬」で済ませ、墓も造らず、押し入れに骨壺をしまっておくケースが激増している。今日押し入れや物置に眠る骨壺は1200万体を超えているというデータがある。葬式がなく、墓も造らないとなると、お坊さんと石屋さんは食べていけなくなる。「墓じまい」もどんどん進んでいる。大騒ぎである。キリスト教を苦しめた仏教界が、今最後の時を迎えているのである。キリスト教を長く暗い墓穴に閉じ込めた墓石は、今このように取り除かれる時を迎えた。キリスト教は牢から解放され、大きく羽ばたき舞い上がることが出来る時を迎えたのである。ハレルヤである。喜びをもって宣教に励もうではありませんか。
(4)ブライダルの部分をキリスト教が主権復帰したことは重要である。
これは神道に対する勝利である。今後、葬儀も教会式で行うようにならなければならないし、押入れに眠る死者たちの骨壺の納骨堂の用意も必要になるだろう。これが出来れば仏教に対する勝利である。
一方我々の重要な使命はキリスト教会の刷新である。宗教改革を起こさなければならない。昨年ルターの宗教改革500年を迎え、様々な記念行事が行われたが、新たな宗教改革が必要であるという主張をした人はいない。唯一私だけがそれをした。2000年語り継がれてきたケリュグマの誤っている部分を正さなければならない。イエスは十字架に掛かるために来たのではない。神の国を再建するために来た。図らずも人間の不信仰に遭い、十字架に掛けられるところとなったが、それはイエスの本意ではなかった。そこで復活して、霊人体になってでも、もう一度伝道し、弟子たちを立てようとした。弟子たちは復活のイエスと出会った時、初めて、本当に、イエスを心から信じた。たとい八つ裂きの刑に遭っても二度とイエスを裏切るようなことはしないと決心した。このようなものが120名集まった時イエスは安息し、天に昇られた。実は120数は世界を象徴する数で、120ヶ国の王がイエスに従ったということの象徴になるからである。世界の象徴的救い主としての座を確立できたので、安心して天に昇られた。これがイエスの昇天である。復活から40日目のことであった。その10日後、天から聖霊が降った。この聖霊に押し出されて世界伝道が始まり、今日の教会が生まれてきた。
宣教の中心は初め復活であった。これを神の出来事として語ることには何の問題もなかった。しかし、十字架である。これをどう評価するか。どうみても十字架は人間の不信仰とイエスの宣教の失敗としか思えない。それを神の出来事にするため福音書記者たちは様々な神学的操作を加えた。黒を白と言いくるめるために、「十字架予言の言葉」というものを編集句として挿入したり、イエスの言葉に何かを書き加えて別の意味にしてしまったり、旧約聖書の本来は別の意味の言葉を十字架予言の言葉だと引用した。こうして十字架は神の御心であり、イエスの生存目的であるとされてしまった。
およそ100年前から始まった聖書の精密研究―高等批評という―の結果、福音書の構造やカラクリが次第に明らかにされてきた。そして、福音書の記述の多くが真実を伝えていないことが分かってきた。このことが教会の伝道の低迷に繋がっている。1970年代に教団紛争というものが起こったが、これも高等批評の成果の基に教団改革をしようとした神学者たちと伝統教理にとどまっていた牧師たちとの間に起こった紛争と見ることが出来る。神学者たちは「贖罪のキリスト」に代えて、「差別と闘うキリスト」「貧民救済のキリスト」などいわゆる「解放の神学」を提示するが、十字架の中に神の愛の結晶を見てきた牧師たちには到底満足できるものではない。加えてこの改革運動は理論上の不足を多分にマルキシズムに頼るところから、実際は左翼革命運動に飲み込まれてしまうという欠点を持っていた。
(5)我々は今、我々の前にある、聳え立つ大岩が次々と崩壊してゆく現象を目撃する。
キリスト教会を救わなければならない。矛盾だらけの伝統教理をなぞる様なことではそれはできない。十字架の愛の深層を更に掘り起こす、巨大な神の愛の神学とそれに基づく地上天国実現の運動を起こしてゆかなければならない。2000年の伝統神学の限界を乗り越え、また高等批評の成果を踏まえつつ、神とイエス・キリストの中に隠された、父と子の涙の道行きを解き明かすものでなければならない。
必ずや人類は救済される。それは神が願っていることだからである。では救われるべき地獄はどこにあるか、地上にある。地獄の形成要素が全て地上にあるからである。妬み、嫉妬、驕り、高ぶり、不信、不実、不忠、裏切り、差別、いじめ、強欲、搾取、略奪、戦争…。イエスはこの地上地獄を救いにやってきた。
これが新しい視点である。この視点に立って、地上天国実現の広範な運動を起こしてゆかなければならない。今やその絶好のチャンスがやってきているのである。ハレルヤ‼
キリスト教不毛の荒れ地、砂漠の北陸に、信仰と希望と愛の美しい花を咲かせよう。